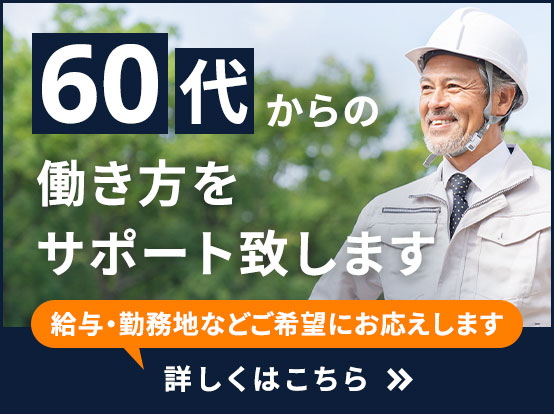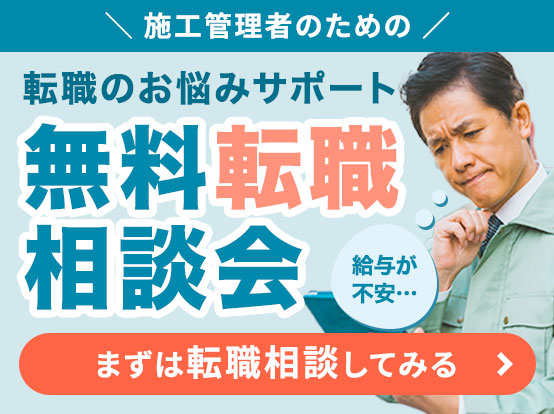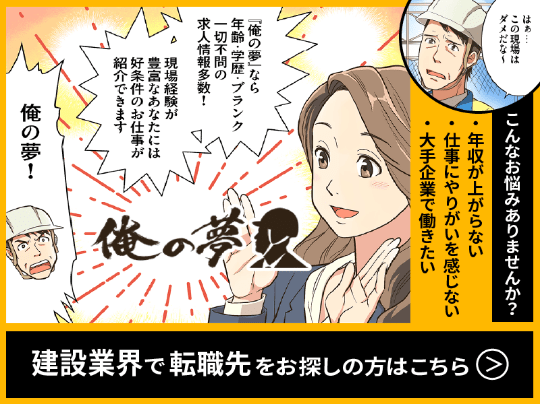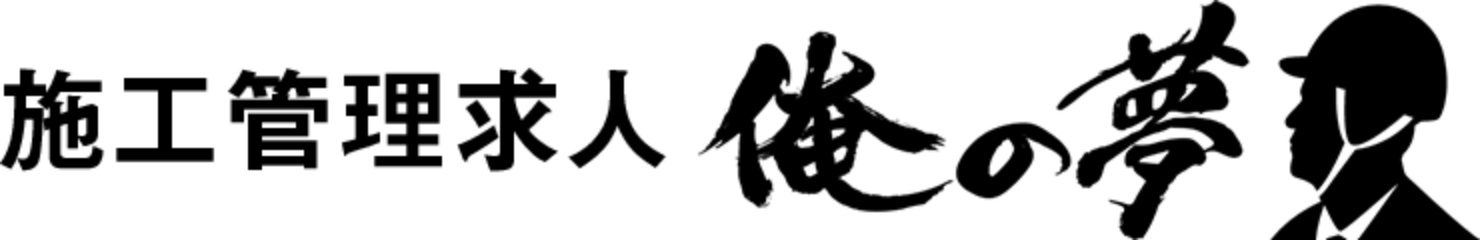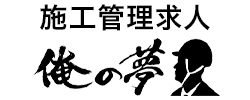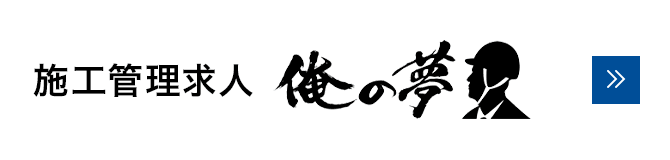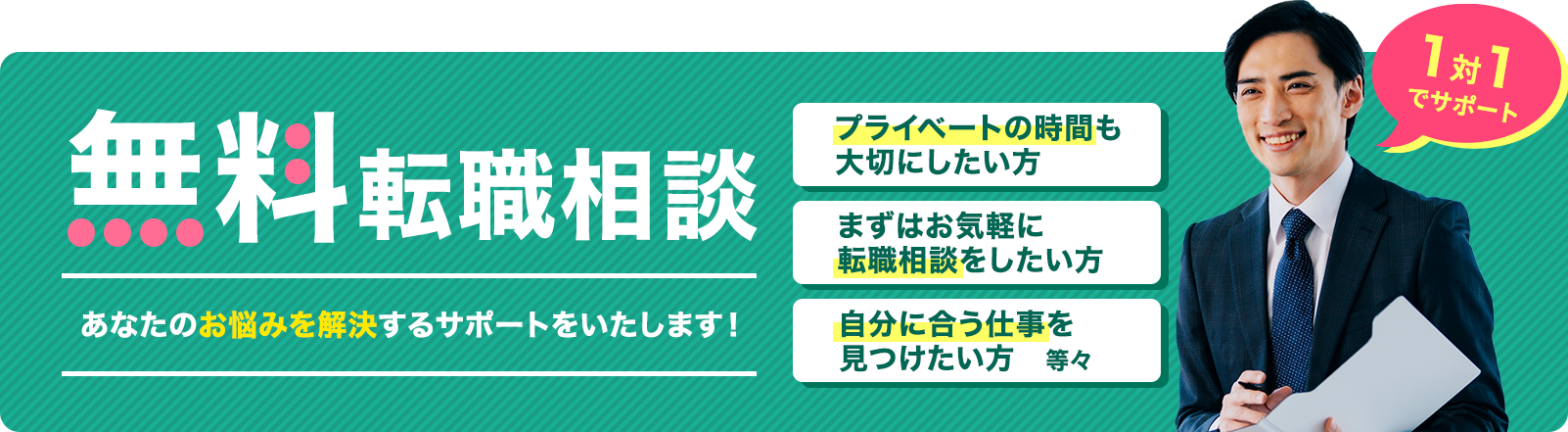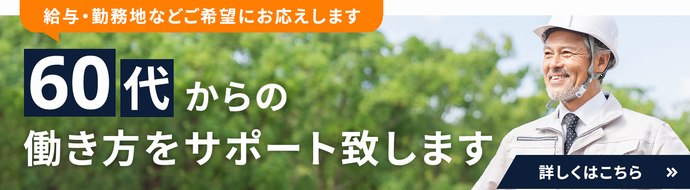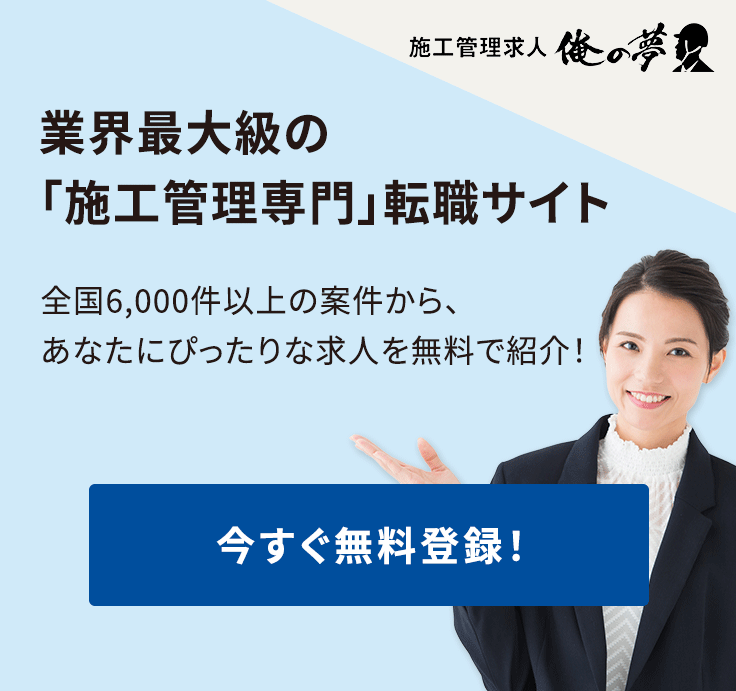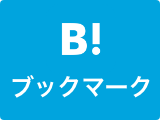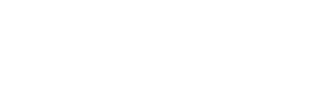石工事に関わる施工管理者がおさらいしたい工法:湿式工法
湿式工法とは、モルタルや漆喰、塗り壁など、水を混ぜて作った材料を使った工法のことです。
材料が乾く時間が必要なので、乾式工法より工期は長くなる傾向にあります。
本記事は湿式工法の特徴やフローなどを紹介します。
湿式工法とは

湿式工法とは、現場で水を混ぜて作った材料を使う工法のことを指します。
モルタルや漆喰、塗り壁などの作業は、湿式工法に分類されます。
工期は乾式工法より長くなりますが、味わいのある質感が楽しめるのが特徴です。
湿式工法のフローと特徴一覧
1.仮留め
鉄筋にステンレス線を絡ませ、止水材などを使って仮留めします。
2.モルタル充填(1回目)
横1弾の仮留めが終わったら、躯体との間に裏込めモルタルを充填します。
目安は高さ1/3ほどとされています。
3.モルタル充填(2回目)
1回目のモルタルが乾いたら、2回目のモルタル充填を行います。
2回目も高さ1/3ほどが目安とされています。
4.次段の石を仮留めする
1と同様に次段の意思を仮留めします。
5.モルタル充填(3回目)
下段の残り部分と、今回積んだ石の高さ分モルタルを充填します。
1~5を繰り返して石を積みます。
湿式工法は石積みのほか、漆喰やモルタル壁などにも使われます。
モルタルを乾かす時間が必要なため、1日1~2段の施工が限界とされています。
無理に石を積んでしまうと、モルタルが石を押し出してしまうので注意が必要です。
湿式工法の特徴
湿式工法は、数十年前までは主流の方法でした。
漆喰やモルタル壁などが多く、一般住宅でも使われています。
湿式工法のメリットには以下のようなものが挙げられます。
- つなぎ目がないため、見た目が良い
- 材料の調合次第でさまざまな風合いが表現できる
乾燥させる時間が必要なため、乾式工法より時間がかかりますが、独特の風合いや質感は代えがたいものがあります。
そのため雰囲気や個性を重視する住宅や、天然素材にこだわった住宅などで用いられています。
また神社仏閣など、伝統工法で作られた建築物は、今でも湿式工法が主流です。
ただし、湿式工法は材料を乾かす時間が必要です。
そのため乾式工法より工期が長くなる傾向にあります。
施工管理者はその点を頭にいれて、工法を選びましょう。
独特の風合いが魅力
現在の主流は乾式工法になりつつありますが、湿式工法はその独特の風合いが魅力です。
職人技で作られた壁や石積みは、乾式工法では出せない味わいがあります。
そのため今でも湿式工法が求められる場所は多く、施工管理者は場所や顧客の要望に応えられる工法を提案する必要があるでしょう。
関連記事:
クサビ式足場の特徴は?足場の組立手順を紹介!
耐震を悩んでいるなら!建物の一番の弱さを補強できる工法や工事ができる「耐震改修」という選択
高所作業とは?安全対策や役立つ講習について紹介!
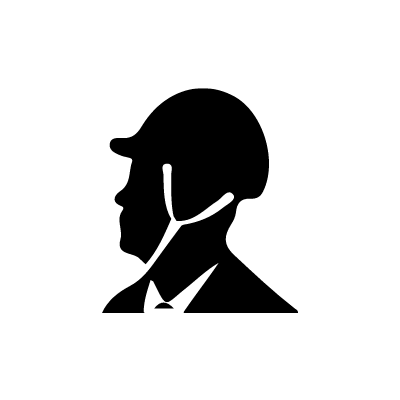
編集部
俺の夢は「施工管理技士の派遣転職」に特化し、業界最大級の求人数、30年以上の転職サポート実績を誇る求人サイトです。
このサイトでは、施工管理技士の方に役立つ情報を「トレンド」「キャリア」「知識」の3つに分けてお届けしています。
運営企業:株式会社 夢真

New Column新着コラム
-
現場のDXを実現する総合ICTサービス「さくレポ」、9月よりリリース
2022.09.22俺のトレンド
-
キヤノンが「RFID 位置情報ソリューション」を開発、大林組と実証実験を開始
2022.09.21俺のトレンド
-
建設業向け生産支援「Photoruction」鹿島建設が導入・インタビュー公開
2022.09.20俺のトレンド
-
「Model Builder」、歩くように3Dモデル内を閲覧できる機能をリリース
2022.09.19俺のトレンド
-
リフォームでスマートホーム化、「サステナブル建築物等先導事業」に採択
2022.09.18俺のトレンド